プログラミング教育が目指すもの【ProGymコラム#1】
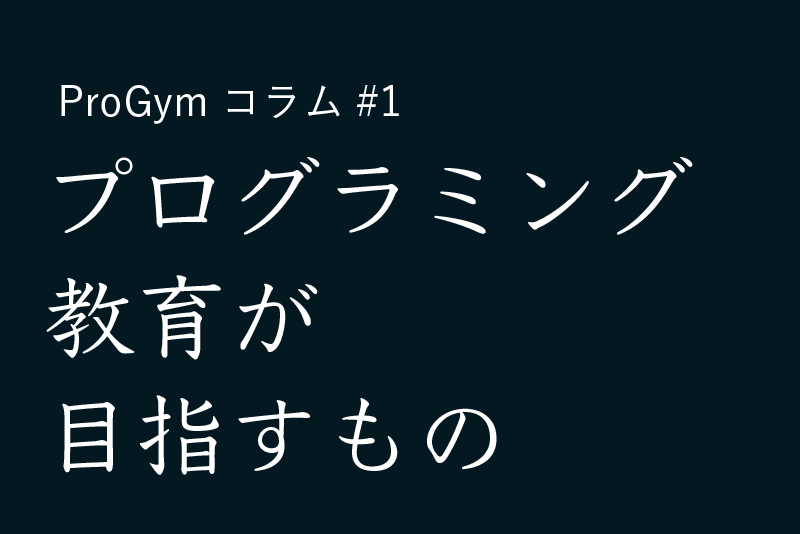
2020年度にプログラミング教育が小学校で必修化されました。2021年度からは中学校、2022年度からは高校でも必修化される予定です。しかし、プログラミング教育と聞いてピンとくる人はどれだけいるでしょう?
文科省の説明資料を要約すると、
https://www.mext.go.jp/content/20200210-mxt_jogai01-100013292_01.pdf
<背景>
少子高齢化と技術革新の進展により、暮らしや働き方が大きく変わっていく中で、「今、学校で教えていることは、時代が変化したら通用しなくなるのではないか」「人工知能の急速な進化が、人間の職業を奪うのではないか」といった不安の声がある。
<目的>
予測できない変化を前向きに受け止め、主体的に向き合い・関わり合い、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となるための力を子どもたちに育む学校教育の実現を目指す。
<具体策>
「情報活用能力」を言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけ、小・中・高等学校を通じてプログラミング教育を充実する。
小学校:
文字入力など基本的な操作を習得、新たにプログラミング的思考を育成
中学校:
技術・家庭科(技術分野)においてプログラミングに関する内容を充実
高等学校:
情報科において共通必履修科目「情報I」を新設。全ての生徒がプログラミングのほか、ネットワーク(情報セキュリティを含む)やデータベースの基礎等について学習
背景と目的までは、「その通りだよね〜」と言う感じで、特に違和感はありません。ところが、具体策を見ると、唐突にプログラミングという言葉が出てきて、飛躍した感じに。子供たち全員をプログラマにしようとしてるの?みんながプログラマになったら、目的が達成されるの??という疑問が沸々と。。。
文科省の説明そのままではよく分からないので、自分で考えてみようということで、とりあえずプログラミングという言葉を調べてみました。
プログラミングとは外来語で、英語のProgrammingのこと。
Programという動詞の現在分詞・動名詞で「Programする」ということ。
名詞のProgramの意味は、予定表、計画、演目一覧、番組一覧など。
プログラミングとは、プログラム(計画)を作ること、物事が計画通りに進むようにすること。
プログラムと言うと、テレビの番組表、運動会やコンサートの冊子、新人教育プログラムなどが思い浮かびます。と言うことは、運動会やコンサートなどの演目と進行内容を書いたものを作る、計画に沿って新人に教育を行う、ということもプログラミングだと言うことができます。コンピュータやソフトウェアを制御することだけではなく、プログラミングと言う言葉をもう少し広く捉えてみた方がいいかもしれません。
「計画を作ってその通りに物事が進むようにする」ために、まずどのように物事を進めたいのかをはっきりさせなければ、正しい計画は作りようがありません。計画が正しくなければ、計画通り物事を進めることができても、結果は中途半端なものになるでしょう。
しかし、「予測できない変化」の中で、いろんな立場の人がいろんなことを言うでしょうが、どの考えが正解なのかは誰にも分かりません。分からないからと言って、足して割ったような妥協案に落ち着いてしまえば、誰も結果に責任を持てないでしょう。
これに対して、「前向きに受け止め、主体的に向き合う」とは、どの考えが信じるに足るかを自分で判断する、信じられるものが無ければ自分で考える、ということだと思います。
物事をどう進めたいのか信じるに足る計画を作れたら、次はどうやって「計画通りに物事が進むようにする」かです。計画の内容次第で必要な実現手段は異なるし、制御方法も様々です。
単一の手段で実現できることはほとんどなく、手段の組み合わせ方は星の数ほどあります。一人で全てをこなすのは不可能なので、役割分担が必要になります。これに「主体的に関わり合う」「自らの可能性を発揮する」とは、自分の得意分野を知りその能力を伸ばし、必要とされる役割を果たすということだと思います。
ここまでで、目的とプログラミングの関係が何となく分かったような気がします。それを踏まえて具体策をもう一度見てみましょう。
やはり、コンピュータやソフトウェアを制御するという意味でのプログラミングに限定されていることは否めませんが、既存のカリキュラムでここまでカバーしているので、足らない部分を今回追加したということなのかもしれません。。。
いずれにしても、子供たちの学び・成長の場は学校だけではありません。学校ではカバーできないこともたくさんあるでしょう。家庭や様々な課外活動の場を含めて、社会全体で補完し合わなければなりません。考え方や目的を共有しながら、それぞれの場の特徴を活かして子供たちの成長をサポートしていければと思います。
「予測(理解)できない変化を前向きに受け止め、主体的に向き合い、関わり合い、自らの可能性を発揮する」ためにProGymは、幅広い創作活動に挑戦する中で、何をしたいかを自分で考え、自分の得意分野を知りその能力を伸ばす環境を提供していきます。
(文)白髪のおじさん
人気の記事
-
【2022年版】とってもわかりやすいMinecraftインストール方法(アカウント作成〜体験版・製品版にするまで)【PC Java版】
2022年6月7日
-
【ちゃんと動きます】ついに降臨!あの有名なウンコが最強装備でマイクラの世界にやってきた!
2020年4月13日
-
小3がMinecraft(JAVA版)のJointBlock(Mod)を使って、動く戦車をつくってみた。弾丸の発射も可能!
2020年4月8日
-
大人気のウンコ人形をBlenderで3Dモデル化してUnityで踊らせてみました。
2020年7月1日
-
\閲覧数32,000回突破中/鬼滅のタイピング遊郭編バージョン【鬼滅の刃 遊郭編】
2021年10月20日
イベントレポート
more-
【第4回】Nintendo Switch『ナビつき!つくってわかるはじめてゲームプログラミング』無料体験会イベントレポート
2023年3月23日
-
【第3回】Nintendo Switch『ナビつき!つくってわかるはじめてゲームプログラミング』無料体験会イベントレポート
2022年8月3日
-
総務省主催「地域ICTクラブ 地域連携推進シンポジウムin広島」でProGymを紹介させて頂きました!
2022年2月9日
-
第72回CoderDojo紙屋町レポート
2021年11月22日
-
【第2回】Nintendo Switch『ナビつき!つくってわかるはじめてゲームプログラミング』無料体験会イベントレポート
2021年10月25日

